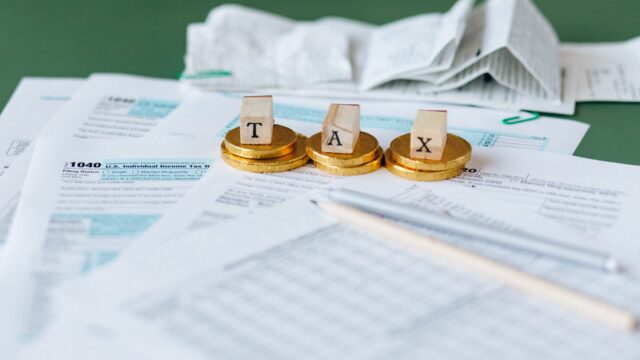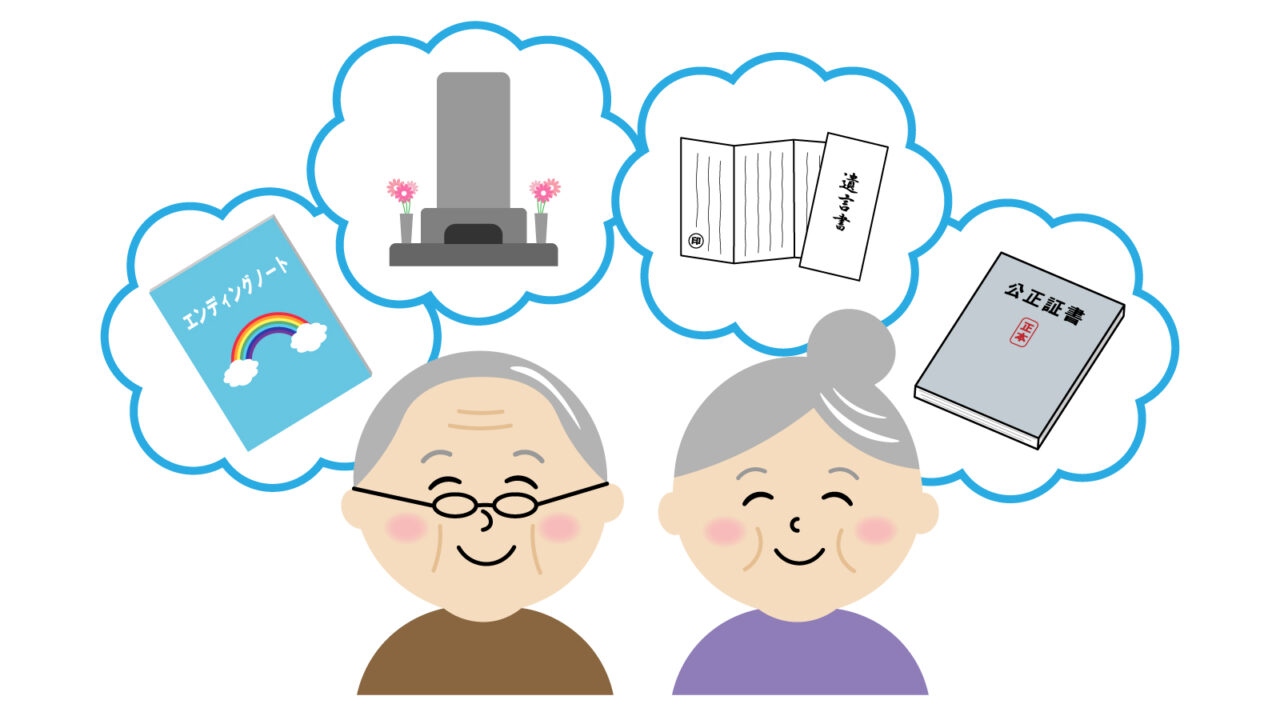自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを知りたい
遺言書を書こうと思うが、基本的な書き方が知りたい
こんな話にこたえます
記事の信頼性
公的金融機関出身/独立後相続コンサル30年超/終活事業者・士業との協働で相続問題に携わる/保険代理店の経営経験あり/MBA/経営管理修士/FP/証券外務/任意後見人受任者/民事信託組成協働/50代/男性
読者へのメッセージ
相続に備えて、遺言書を書きたいと思う人が増えてきました。書店でも、メディアでも、普通に遺言書のことが取り上げられている時代、残された家族が不幸にならないようにするためにも、遺言書の作成はとても重要であることは間違えありません。しかし、せっかく書いたのに書き方のルールを間違えてしまうと無効になってしまうため、正しく書いておく必要があります。
本記事では、遺言書の種類と、その進め方がご理解いただけるようになっております。また、実際には、家族や財産状況が異なるので、できる限り、公証人や、弁護士、税理士等の遺言書作成の専門家に相談の上書くことをお勧めします。
目次
■遺言書の種類
■自筆遺言証書の2パターン
■公正証書遺言作成の流れ
■遺言書の種類
遺言書の種類として、特殊なものを除き、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
| 概略 | 遺言者の自書で全文作成(但し、財産目録等の一部はパソコン作成可能) | 証人2名以上の立ち合いのもとで、公証人が作成する遺言書は公証役場にて保管 | 内容は秘密のままで、存在のみを公証人が照明する遺言 |
| メリット | 費用は無料、又は安価な費用で作成可能 | ・不備、紛失リスクがない
・内容の相談が可能なので、遺留分等に対応可能 |
・全文パソコン等での作成可能
・内容を知られることがない |
| デメリット | ・財産目録以外は全文自書のため負担が大きい
(法務局利用のない場合) ・家庭裁判所の検認が必要 ・紛失リスクあり |
・公証役場での作成等費用がかかる
・信託銀行等を通じての作成は、作成の手数料がかかる |
・公証役場での費用がかかる
・家庭裁判所の検認が必要 ・内容の不備があった場合、無効になる可能性あり ・保管は自分のため紛失リスクあり |
| その他 | 自筆証書遺言補完制度の活用で、法務局に預けることができる | 2014年4月から公正証書遺言がデジタル化されている | 公正証書遺言に比べ、作成件数が少ない
(年間100件程度) |
秘密証書遺言は、一覧表のとおり取扱件数が全国で年間100件程度と少なく、本記事では、実質取り扱いが多い自筆証書遺言と公正証書遺言の二つのどちらかをご説明します。
■自筆遺言証書の2パターン
パターン① 従来の自筆証書遺言
≪作成からの流れ≫
遺言内容の決定
財産目録を作成して、誰に、何の財産を相続させるのか決めます。
↓
遺言書作成
↓
相続発生
↓
家庭裁判所での検認が必要(不備による無効になる可能性あり)
↓
遺言に沿って手続き開始
パターン② 遺言書保管制度を活用した自筆証書遺言
≪作成からの流れ≫
遺言内容の決定
財産目録を作成して、誰に、何の財産を相続させるのか決めます。
↓
遺言書作成
↓
法務局にて保管(事前予約必須)
・形式について不備の確認(内容についてはコメントできない)
・費用1件3,900円
・原本保管、画像のデータ化
・指定者(遺言者の推定相続人、受遺者、遺言執行者等3人まで可能)
↓
相続発生
↓
指定者へ保管通知(検認は不要)
↓
遺言に沿って手続き開始
(参考)
自筆証書遺言の無効になるケース
・全文タイプ打ち(財産目録はタイプ打ち可能)
・代筆
・署名・捺印がない
・日付なし、又は日付が「〇月吉日」とあいまい
等
■公正証書遺言作成の流れ
大まかな流れは下記のようになります。
遺言内容の決定
財産目録を作成して、誰に、何の財産を相続させるのか決めます。
↓
公証人との面談
最寄りの公証役場に相談予約を入れて、公証人と面談し遺言内容を検討します。
少なくとも2回以上は相談して、内容に間違いがないか確認します。
↓
証人の選任
公正証書遺言の作成時には、証人2名の立会いが必要になります。
信頼のおける知人等がいれば、依頼することは可能です。
↓
必要書類の収集
↓
遺言書の作成「原本」・「正本」・「謄本」の3つ
公証人・証人立会いにて3つすべてに署名・押印
・「原本」・・・公証役場に保管
・「正本」・・・自宅保管、原本と同じ効力をもつ、遺言による相続手続きはこの正本を活用。
・「謄本」・・・自宅保管、原本の写し、あくまでコピーであり、謄本での相続手続きは不可
内容の確認のみ
※ 公証人と公証役場で作成は可能ですが、税金や法律等、不安がある場合は、弁護士、税理士等に依頼します。その際には、「正本」を預けておきます。
↓
相続発生
↓
遺言に沿って手続き開始(検認は不要)
以上、遺言書の種類と、その作成の進め方について見てきました。実際に、どのように書くのかは、公証役場の公証人、弁護士、税理士等の専門家に相談していただくことをお勧めいたします。皆様の遺言書作成がスムーズにいきますよう、願っております。